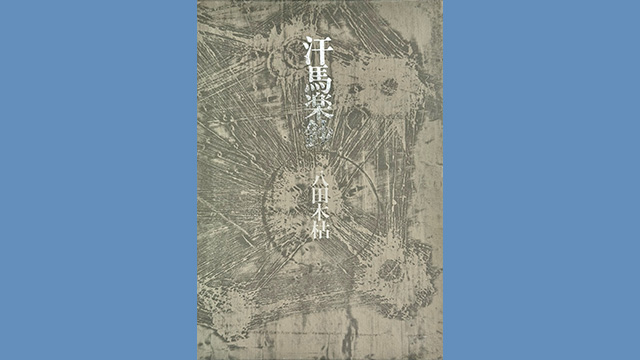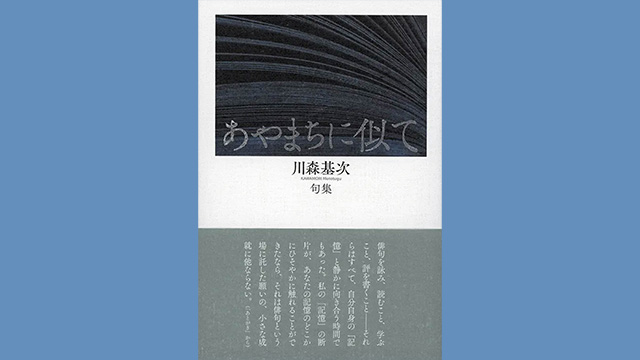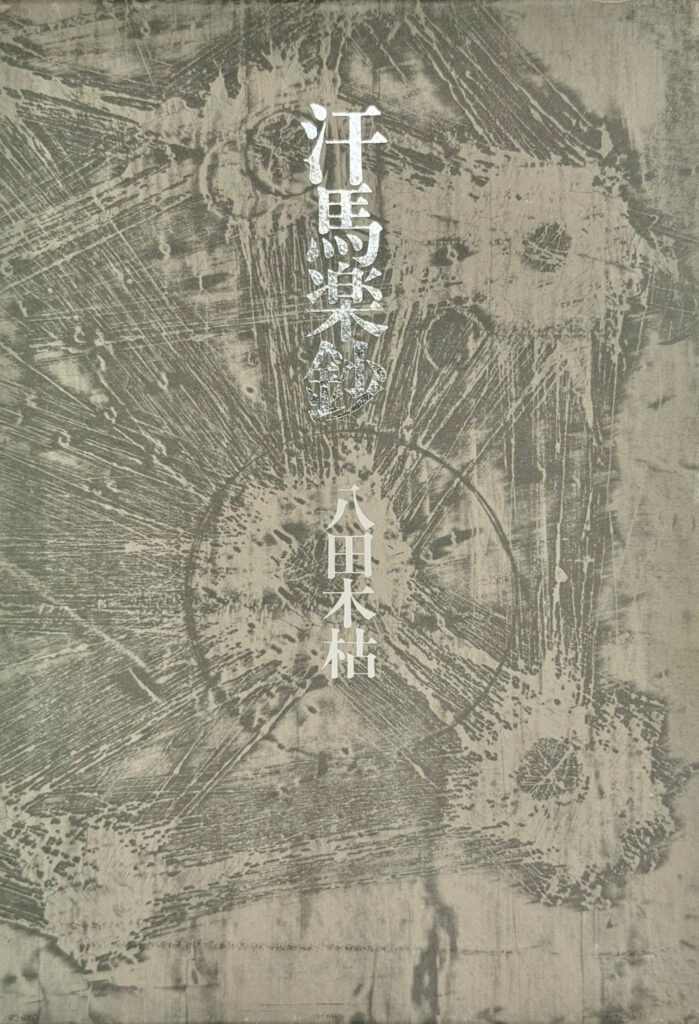
発行日:1988年9月10日
出版社:深夜叢書社
著者、八田 木枯(はった こがらし、1925年1月1日 – 2012年3月19日)は、日本の俳人。
2025年は生誕百年にあたることからメモリアルイベントが企画されています。
句集評
薔薇活けて寝るや身のうちすべて棘
『汗馬楽鈔』より
夢分析的に言えば、薔薇は抑圧された欲望や自己愛の象徴であり、それを部屋に置いたまま眠りに入ることは、無意識に対して扉を開く行為です。下五の「身のうちすべて棘」は、夢の中でしばしば起こる自己同一化の極端な表現と読めます。本来は外部にあるはずの棘が、いつのまにか「身のうちすべて」へと転移している。この転移は、夢における象徴の内面化そのものであり、美や愛を求める主体が、その代償として痛みや攻撃性を全面的に引き受けてしまった状態を示します。薔薇を活けた主体と、棘に満たされた身体とは、夢の論理によって同一化され、分離不可能になっています。
この句の怖さは、棘による痛みが描写されていない点にあります。痛いとも、血が出るとも言わない。ただ「すべて棘」と断言することで、主体はすでに痛覚を超えた段階、つまり防衛や自己罰が常態化した心理状態にあることが暗示されます。夢分析的には、これは欲望と自己傷害が分かちがたく結びついた心的構造の表出であり、美しいものを求めるほどに自分を傷つけてしまう無意識の反復を示していると言えるでしょう。
結果としてこの俳句は、眠りという夢の入口を通して、自己愛と自己否定、快と痛の混淆を一瞬で可視化しています。薔薇は外に活けられているはずなのに、目覚めたとき、棘はすべて自分の内側にある――その夢的逆転が、静かで残酷な余韻を残す一句です。
十五句抄出
寒梅や鏡老いたる人の家
麦藁帽妙にふかくて淋しいぞ
満つ水のさかのぼりゆき枯野果つ
くちづけの宵の青さは秋鯖か
凍蝶に天あり天をとばざるも
汗の馬なほ汗をかくしづかなり
汗の馬芒のなかに鏡なす
家じゅうの柱のうらの稲光り
葬列のあと風が吹く蝗の背
冬鵙来るくちづけの時必ず来る
下駄穿いてゆく木がらしを愛すごとく
家に奥が無くて戦後の羽織の母
情死体ありしゆふぐれ葱きざむ
夫婦となり空につめたき日が一つ
外套のままの仮寝に父の霊
記:川森基次